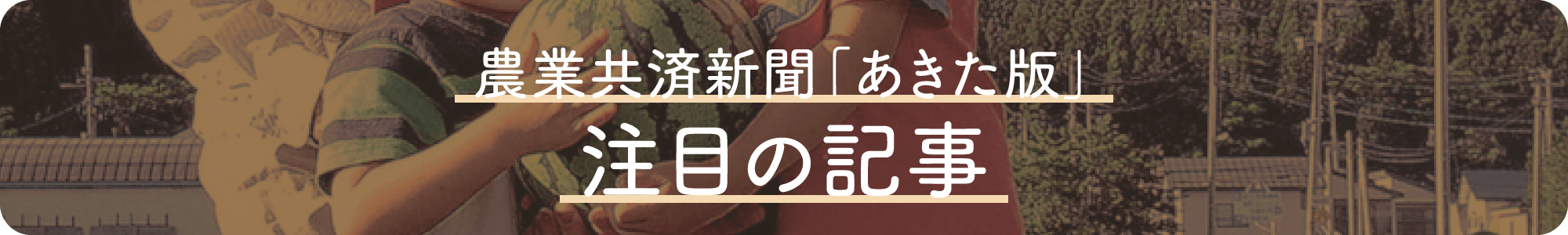あきた版7月1週号
水稲・大豆 有機農産物に転換中 消費者ニーズを重視 - 田村健さん
大潟村の田村健さん(55)は主食用米9・5㌶と加工用米2・2㌶、大豆3・3㌶を栽培する。小麦2・2㌶を後作し、2年3作体系で連作障害を防ぐ。有機JASの転換期間中有機農産物認証を受ける1・1㌶の圃場では水稲と大豆をローテーション。その大豆の一部を、みそに加工する。土地利用効率を高めて、持続可能な地域農業を追求する。
田村さんは就農3年目。妻と共に農作業に従事し、田植えの際は親族や学生らを5人ほど雇用する。監査役を務める株式会社大潟村カントリーエレベーター公社に全量を出荷する。近隣農家と積極的な情報交換に努め、経験則を学ぶという。
父から2023年に経営移譲を受け、化学農薬と化学肥料不使用で有機JASに準じた方法の大豆栽培も引き継いだ。昨年から有機栽培に転換中の圃場では「あきたこまち」を作付けし、今年は大豆「リュウホウ」の生産に取り組む。5月中旬に鶏ふんを1㌧散布し、6月中旬に播種する。カルチベーターで中耕した後、手作業で雑草を取り除く。11月上旬に収穫を迎える。播種機とカルチベーター、汎用コンバインは近隣農家と共同で使用する。
同村の慣行栽培の平均収量は、昨年で10㌃当たり192㌔。化学農薬と化学肥料を使わない栽培では半数ほどにとどまるという。「近年は猛暑で大豆が雑草の生命力に負けてしまい、生育不良となった。夏場の草取りは非常に危険で、早朝の数時間しか行えない」と管理の難しさを話す。セーフティーネットの重要性を理解し、父が決めた収入保険の加入を続けている。
就農前は銀行員だった田村さん。ビジネスマッチングを担当した際、需要と供給の不均衡を目の当たりにしていた。「有機農産物のニーズは根強く、特に都市部の病院や老人ホームなどから多数の引き合いがあった。消費者に求められているものを作りたいという意識につながった」と振り返る。
同村では有機栽培した米と大豆を使い、日南工業株式会社大潟村加工センターでみそに加工される。米と大豆を270㌔ずつ使用し、塩分濃度は12%に調整。6カ月熟成した後、酒精を添加し1㌔にパック詰めする。年間約3千㌔を製造し「秋田みそ」として販売している。同センターの高橋真さんは「豆が軟らかくなり過ぎないよう蒸し加減を見極めている。輸出なども検討し、村内産のおいしいみそを売り出したい」と話す。
田村さんは極端な物価高騰に危機感を抱き、永続的な農業を模
索する。有機栽培も付加価値を高める方法の一つだという。「規模拡大を行わずとも自立できる中小規模経営体の増加が、地域の持続性向上につながると考える。栽培技術の向上と併せて実践したい」と前を向く。
次号をお楽しみに!